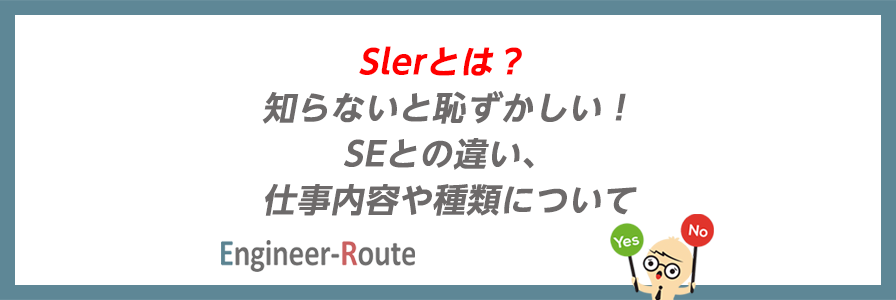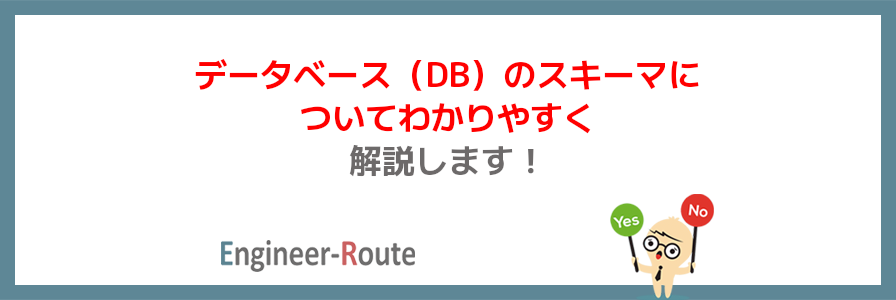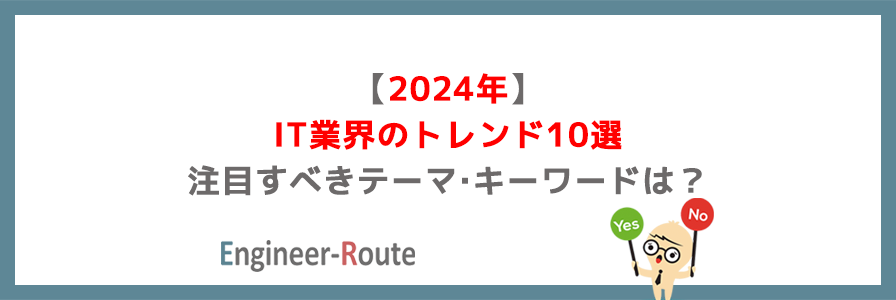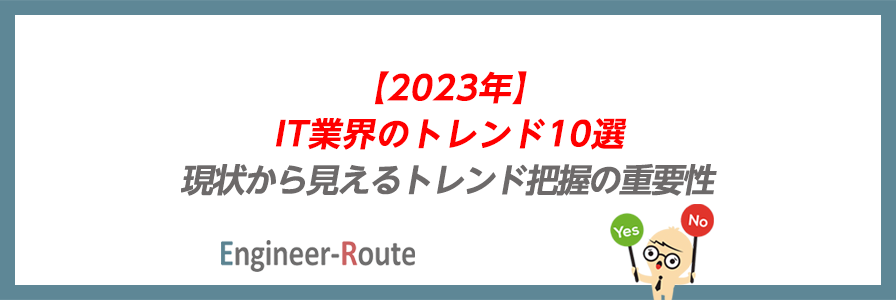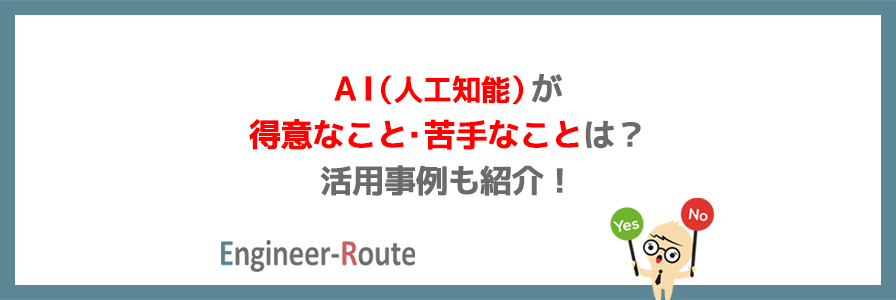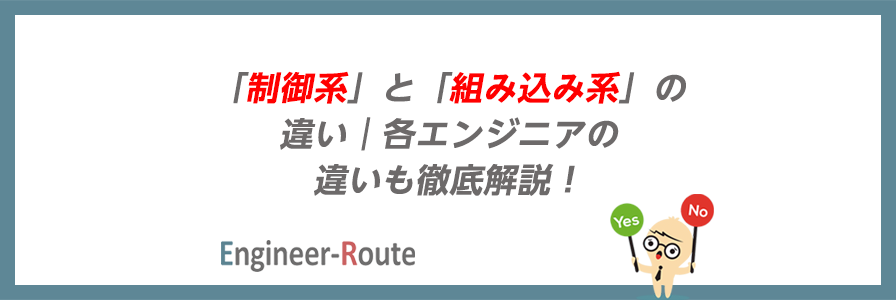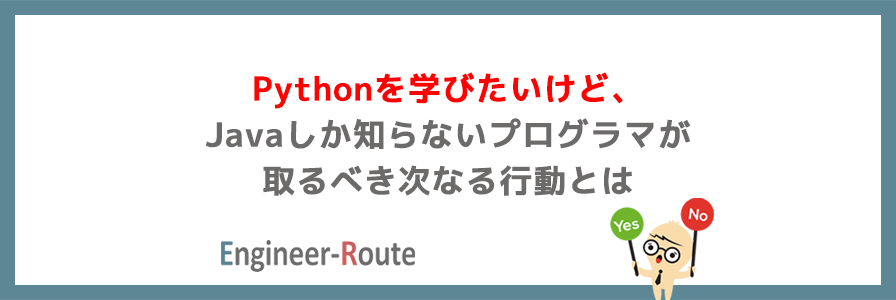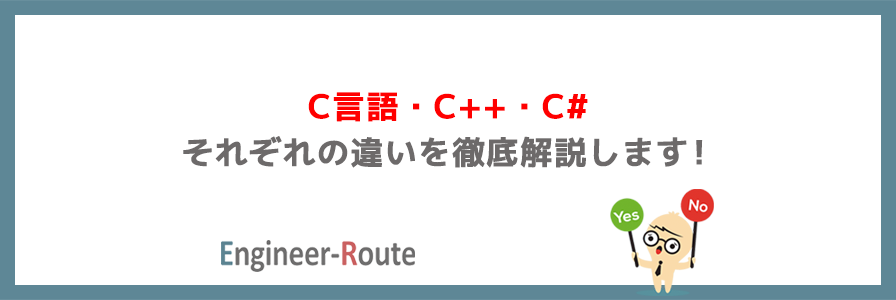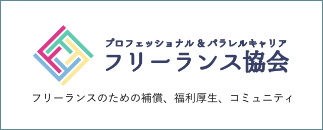SEに向いている人・向いていない人とは?
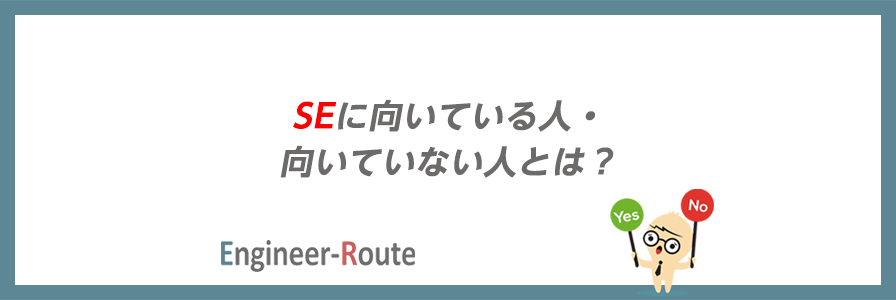
SEになるには、プログラミングへの適性や言語化能力などが必要となります。
ですが、「自分はSEに向いているのか?」と悩むこともあるでしょう。
そこで今回は、SEに向いている人やSEに向いていない人の特徴などをご紹介します。自分がSEに向いているのか確かめたい方や、今後SEを目指したい方などは、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
SEの仕事について
SE(システムエンジニア)の仕事は、プロジェクトや企業によって異なるのですが、主に以下のようなものがあります。
ヒアリングと要件定義
SEは、まずクライアントの要望をしっかりヒアリングすることからスタートします。SEは、クライアントがどんな問題を解決したいのか、どんな機能が必要なのかをうまく聞き出し、構築するシステムを提案するのです。
ヒアリングの主な目的は、クライアントがシステムを導入することでどんな結果を望んでいるのかを聞き出すことです。
しかし、ヒアリングは開発に携わる全てのSEが行うわけではありません。
ヒアリングを担当するSEは、クライアントの要望に応じて何を作ればよいのかを明確にし、ほかのSEに伝えるスキルも必要です。
基本設計と詳細設計
クライアントの要望に合わせて行う設計業務では、大きく分けて基本設計と詳細設計の二つがあります。
基本設計は、実際に作るものの動きや見た目などを決めるための設計です。表面的な部分の設計とイメージするとわかりやすいでしょう。
詳細設計は、基本設計の決定後に実際にプログラミングできるように細かい部分を決めることです。
詳細設計では開発で使うソフトウェアやツール、コーディング規約、処理のフローチャート図、ネットワーク構成、データベース設計などを決めていきます。
テスト
システム設計や構築作業を経て機能が作成されたら、正常に動くことをチェックするためのテストをします。
テスト作業は、ユーザーが実際に利用することを想定して行います。テストでバグが見つかった場合、その箇所の修正や設計見直しなどを行う必要があります。
また、一つの機能のテストが完了しても、連動する機能が完成したらそれらを結合したうえでまたテストを行います。
このようなテスト作業は、SEの仕事の中でも特に根気のいる仕事と言えるでしょう。
SEに向いている人とは?

SEとして働く場合、自分の性格や仕事の仕方がSEに向いているのか気になりますよね。
次は、SEに向いている人の特徴を見ていきましょう。
プログラミングが好きな人
SEの仕事の中でもプログラミングは主要なスキルと言えます。チームにプログラマーがいなかったり、いても手が空いていなかったりする場合、SEもプログラミングを行う必要があります。
プログラミングができるとおおよその工数が計算できるようになるので、見積もりの精度も向上します。
このような理由から、SEはプログラミングをスムーズに行う上でも、プログラミングが好きであることが大切です。
コツコツと地道な作業ができる人
SEの仕事は、全体的に見てもコツコツ地道に行うことが多いです。案件によっては、作業時間が数ヶ月単位にまで及ぶこともあるのです。
また、テスト作業においてはいろいろなシチュエーションを想定し、問題がないかをチェックする必要があり、根気のいる作業となります。ほかにも、仕様が変更された場合やバグが発見された場合は、これまで行ってきた作業をやり直す必要もあります。
こういったSEの仕事の特徴から、コツコツと地道な作業が好きな人はSEに向いていると言えるでしょう。
見直し・改善する向上心を持っている人
SEが行う設計や構築の工程では、改善や見直しが求められるケースも多いです。クライアントの要望をもとにつくった設計書がクライアントの理想と異なる場合、SEはその見直しや改善を行う必要があります。
また、見直しや改善作業は、開発過程やテスト段階でバグが確認された場合にも発生します。特に、バグが見つかった場合には、原因となっている箇所を見つけるために見直し作業を行う必要があります。
納品物の精度を高めるといった意味でも、見直しや改善を行う向上心がある人は、SEに向いているでしょう。
コミュニケーションスキルが高い人
SEの仕事は、クライアントの要望をしっかりヒアリングすることから始まります。そのためには、クライアントとの十分なコミュニケーションを取ることが大切です。
開発の現場では、何人かのSEが共同で作業を進めることも少なくありません。このような現場の場合、プロジェクトマネージャーやリーダー、ほかのSEとも十分なコミュニケーションを取り、プロジェクトをスムーズに進めていかなければなりません。
SEは人間関係を円滑にすることが、仕事を進める上で大切になるので、コミュニケーションスキルが高い人がSEに向いています。
変化を拒まない人
ITの技術は、社会で広く使われており、日々新しいものが生まれています。
例えば、AI(人工知能)は今では製造業や小売業など多くの業界で使われていますが、数年前は、ビジネスに使えるとはあまり考えられていませんでした。
ほかにも、インターネットやスマートフォンなど同じような事例は多くあるので、これからも想像がつかないようなIT技術が登場し続けるでしょう。
そんな中、SEはITの専門家として、新しい技術に柔軟に対応していくことが大切です。特定の手法や技術にこだわらず、常に変化を受け入れる姿勢を持つ人は、SEに向いています。
SEに向いていない人とは?

SEに向いている人もいれば、SEに向いていない人も存在します。最後に、SEに向いていない人の特徴をご紹介します。
ものづくりが嫌いな人
ITシステムを構築することは、建築と似ている部分があります。チームのメンバーでお互いに協力し合い、想像力と細かな作業を積み重ねながら一つの作品を作り上げていきます。
SEの仕事は、クライアントの要求通りのITシステムを構築して相手に喜んでもらえると、やりがいや達成感を感じられるのではないでしょうか。
このようなものづくりが嫌いな人は、SEが向いていないと言えます。
ITに興味がない人
SEはIT職の一つなので、IT業界やIT事態に興味がない人はSEに向いていないでしょう。
ITに興味がないと、スキルアップやキャリアアップなどのモチベーションを保つことが難しく、実行に移すこともできません。
また、ITに興味がないわけではないけれど、IT分野に苦手意識があるという人も、SEとしてスムーズに仕事を進めていくことが難しく、モチベーションを維持しながら働くのは困難でしょう。
パソコンが苦手な人
SEの仕事では、多くの作業はパソコンを使って行います。そのため、パソコンを使いこなすためのスキルが必要となります。
また、クライアントとのオンライン会議やほかのSEとの連絡・情報共有などの場面でも、パソコンは必要不可欠です。
パソコンに対して苦手意識がある人は、作業自体についていけなくなる可能性があるので、SEの仕事は向いていないでしょう。
まとめ
SEは地道な作業も多いですが、周りとコミュニケーションを取りながら仕事をすることもあるので、集中して作業に取り組めるスキルやコミュニケーションスキルが必要となるでしょう。
そんなSEには、向いている人や向いていない人の適性があるので、自分でSEの仕事が合っているのか確かめてみても良いかもしれません。
ぜひ、SEの仕事内容を詳しく知り、自分の性格や考え方の傾向と照らし合わせ、SEの適性があるか見極めてくださいね。