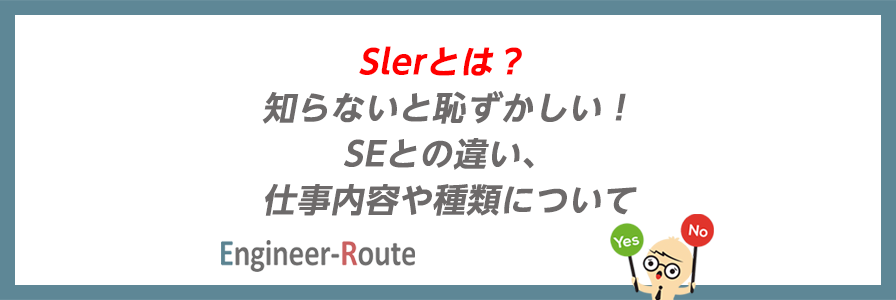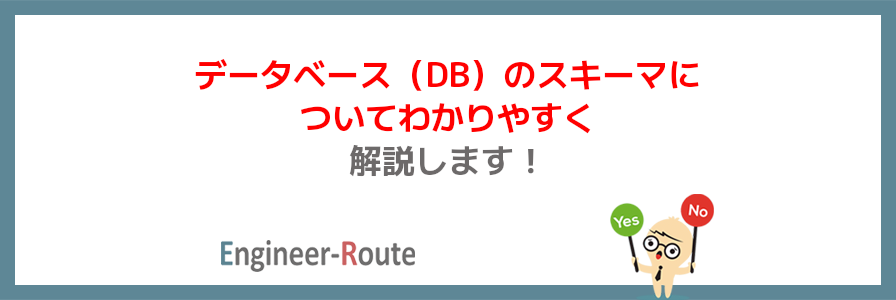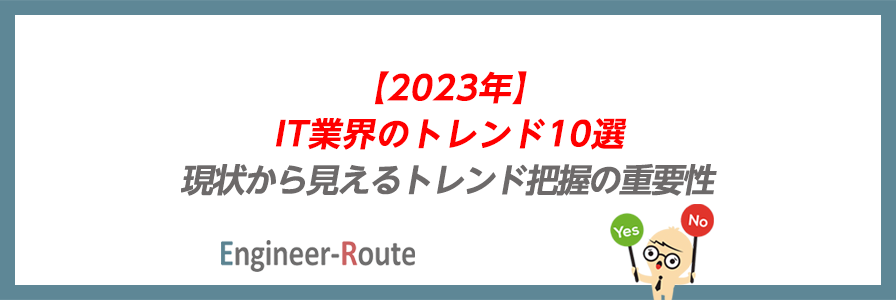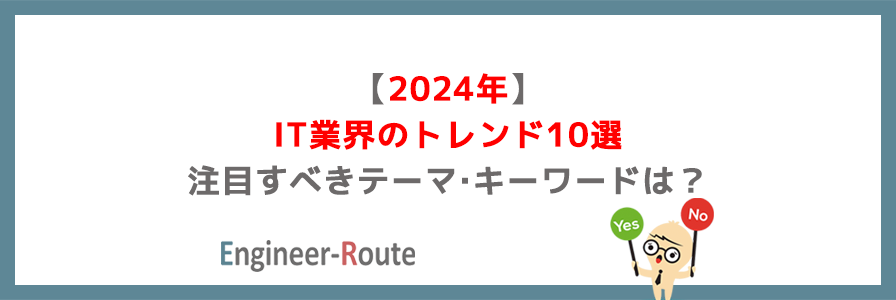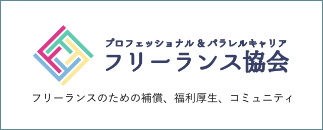フリーランスエンジニアの老後はどうなる?不安を解消するための備え方をご紹介!

自由な働き方が魅力のフリーランスエンジニアですが、その一方で、退職金がないことなど、「老後の資金は大丈夫なのだろうか?」と不安になってしまうこともあるのではないでしょうか。
会社員とは異なるフリーランスエンジニアは、老後の資金もより慎重に考えておく必要があるでしょう。
そこで今回は、フリーランスエンジニアの老後資金について、不安を解消するためにできる対策・利用できるサービスなどをご紹介したいと思います。
目次
フリーランスエンジニアは会社員よりも老後資金が必要?

個人で案件を獲得し働くフリーランスエンジニアは、比較的自由な働き方ができることや、スキルがあれば高収入を目指すことができることなど、魅力も多くあります。
しかし、老後の資金の面では、会社員よりも不安を感じることは多いでしょう。
会社員では、企業によってはまとまった退職を受け取ることができ、老後の資金として活用することができますが、フリーランスエンジニアにはもちろん退職金制度はありません。
また、フリーランスのみでは厚生年金に加入せず国民年金のみとなるため、もらえる年金額にも大きな差があるでしょう。
このように、会社員よりも老後の蓄えが必要になるフリーランスエンジニアですが、スキルや案件に応じて収入を増やしやすかったり、ライフスタイルを柔軟に変化させやすいため、早めに準備をはじめることで、安心して老後に備えることができるでしょう。
フリーランスエンジニアが老後の不安を解消するための備え方
それでは、フリーランスエンジニアが老後の不安を解消するには、どのような方法で備えておくと良いのでしょうか。
意識しておくと良いポイントも含め、いくつか主な方法をご紹介していきます。
金銭の管理をしっかりする

まずは、当然ですが金銭管理をしっかりすることで、貯蓄を習慣化するということです。
月々の生活費や固定費をしっかりと把握し、不要な出費を減らして老後資金として積み立てられるようにするといいでしょう。
アプリやExcelなどを利用して家計簿をつけ、支出を可視化できるようにするのもおすすめです。
また、フリーランスでは保険料や税金の支払いも個人で行うことになるため、その分の支払いも見越して毎月積み立てておくのも良いですね。
受け取れる年金額についても事前に確認しておくと、より資金計画は立てやすくなります。
スキルを磨く
フリーランスエンジニアにとって、案件を獲得し続けるためにスキルは欠かせません。
できるだけ長く収入を得続けられれば、老後も安心できるでしょう。
IT業界は進歩も激しい業界のため、現代であればAI・機械学習分野など、出来る限り最新のトレンド技術を積極的に学び続けられるとより市場価値が高まります。
また、マネジメントや上流工程の経験など、高単価案件を目指せるようなスキルも身に着けておきたいところです。
健康診断は定期的に受ける
会社員であれば定期健康診断を受ける機会も多いですが、フリーランスエンジニアは自身で受診しなければなりません。
健康のために、年に1度の定期検診はしっかりと受けるようにしましょう。
老後もできるだけ長く仕事を続けるためにも、医療費負担を軽くするためにも、健康を維持することは非常に重要です。
また、基本の検診だけでなく、がん検診など、年齢や性別などでのリスクに応じた検査内容を追加することも大切ですね。
年齢を重ねてからの働き方を考える
40代、50代と年齢を重ねるにつれ、働き方を考えることも意識しましょう。
年を重ねて案件数に頼るような無理な働き方をすると、健康を害することにもなりかねません。
高単価案件を受注できるようそれまでにスキルや経験を積んだり、コンサル業や講師業など、身体的な負担が比較的少ない働き方を目指すというのもおすすめです。
フリーランスエンジニアがしておきたいおすすめ対策
前述したように、フリーランスエンジニアでは退職金や厚生年金がないため、自身で資産を形成しなければなりません。
そのための方法のひとつとして、多様な年金制度などを活用するのもおすすめです。
利用できる制度には、主に以下のようなものがあります。
個人年金保険

個人年金保険とは、民間の保険会社が提供しているサービスです。
一定の期間保険料を支払うことで年金のような形で老後に資金を受け取ることができるという仕組みで、契約の内容によっては死亡保障など、家族のために備えることもできるのも魅力です。
保険料控除の対象になるケースもあり、節税の面でもメリットがあるでしょう。
ただ、途中解約をしてしまうと元本割れするリスクがあるため、契約時には無理なく長期的に計画を立てることが重要です。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、毎月の掛け金を自身で設定し、金融商品を運用する形で資産を増やすという仕組みのサービスです。
掛け金は所得控除の対象になるため、節税効果も見込めるでしょう。
デメリットとも言える点は、60歳になるまで原則引き出しができないという点ですが、老後資金として考えるなら大きなデメリットにはならないでしょう。
小規模企業共済制度
小規模企業共済は、個人事業主・フリーランスで働く方が退職金として掛け金を積み立てられる制度です。
こちらも掛け金は全額所得控除となり、節税効果が得られるでしょう。
さらに、積み立てた資金は運用され、それによる運用益も含めて分割金・一時金で受け取ることが可能です。
掛け金は1,000円から設定でき、収入に応じて金額を調整できるのも魅力ですね。
国民年金基金
国民年金基金は、国民年金に上乗せすることで年金額を増やすことができる公的な制度です。
掛け金は毎月定額となり、将来受け取れる年金の額も契約時に確定することができる「確定給付型」のため、安心感もあるでしょう。
ただ、基本的に解約や返金はできないため、長期的に考えて支払える範囲で契約するよう契約時には注意しましょう。
また、公的な制度でリスクが低いのはメリットですが、その分資産運用などで得られるようなリターンはありません。
余裕があれば、リターンが期待できる別の方法と併用しても良いですね。
付加年金
付加年金も、国民年金基金のように国民年金を上乗せする制度です。
毎月400円を追加で支払うことで、200円×加入月数の受給額が加算されます。
毎月の掛け金が少なく手軽に始められるため、こちらも他の方法と併用するのも良いでしょう。
ただ、国民年金の制度見直しによってこちらも見直しが行われる可能性もあるため、状況は確認しながら利用できると良いですね。
まとめ
今回の記事では、フリーランスエンジニアの老後の資金について、その不安を解消するための対策法や、利用できる様々な制度について詳しくご紹介しました。
フリーランスエンジニアでは会社員のように退職金・厚生年金はないため老後を不安に思う方も多いかもしれませんが、事前にしっかりと対策をしておくことで、老後も安心できるような資金計画を立てることができるでしょう。
また、老後のためにも健康は非常に重要です。
無理のない働き方を選ぶことができるよう、スキルや経験はしっかりと身に着けておきたいですね。